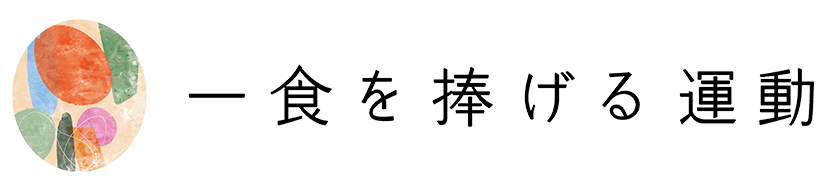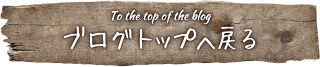- 一食ブログ
- マラウイ赤十字社 学校給食プロジェクトについて
マラウイ赤十字社 学校給食プロジェクトについて
Jun 14, 2025
こんにちは!一食平和基金事務局の池田です。
一食平和基金では、アフリカのマラウイ共和国でマラウイ赤十字社の行なっている「学校給食プロジェクト」を支援しています。今回4月22日から5月2日まで給食支援をしている学校に現地調査のために行ってまいりましたので、ご報告いたします。
マラウイは貧困度が世界第3位といわれる最貧国の1つです(World Economic Outlook (October 2024) – GDP per capita, current prices|IMF)。マラウイでは、多くの人々が農業で生計を立てていますが、収穫期前の10月から2月には食料が不足し、学校に行けない子ども達が多くなります。
一食を捧げる運動の支援金を得て、マラウイ赤十字社はこれまでに24の幼稚園と小学校の子ども達、16,562人に給食を提供してきました。このプロジェクトの主な目的は学校で給食を提供することですが、それだけでなく、地域の人々が協力して管理する学校菜園を作り、その菜園から作られた作物を使って給食を作ることで、支援が終了しても村人達の手で給食が続けられる仕組みを作ることも重要視されています。
今回、私たちはマラウイのチティパ県を訪れました。チティパ県はマラウイの最北端の県であり、タンザニアとザンビアの国境付近にあります。
最初に訪問したチャバ村の小学校では、1年生から8年生までの子どもたちが授業を受けていて、朝の10時に大豆とコーンの粉に砂糖を混ぜたお粥が給食として提供されていました。チャバ村の幼稚園でも給食支援は行われていて、500人近くの子どもたちが、近くのキリスト教の教会で教育が行われていました。
ここでは、アグネス・カラオさん(46歳)と4才のお子さんのお家に行きました。彼女は5人の家族を養っていましたが、彼女はご主人が働かず、家族を養うのにとても苦労していました。彼女はつらそうな顔で、「本当は色んなものを食べさせてあげたい。だけど、何もあげられない。それがとても苦しい。でも、給食のお粥によって、普段はあげられない栄養を補うことができてとてもありがたい」とおっしゃっていました。お粥は子ども達の重要な栄養源になっていました。

アグネス・カラオさんとお子さん

チャバ小学校で出会った親子
チャバ村をあとにし、チェンド村へと移動しました。チェンド村は山を切り崩した地域で、生徒達が学校へ向かう道はとても険しく、大変な思いをして通学をしていました。
村では幼稚園に通っているズフークイ・アビシャイちゃん(5才)のお家を訪れました。そこには生後3週間の赤ちゃんと27歳のお母さん、50歳のお父さんがいました。お父さんは生まれつき足が不自由なために畑仕事や出稼ぎに行けず、お母さんが家族を支えていました。お母さんは、「収入が少なく、生活が苦しい」と教えてくれました。彼女のお家の屋根は藁ぶきですがスカスカの状態で、雨が降ると水浸しになってしまうそうです。彼女は泣きながら「この家を見てください、もう少しお金があれば、雨漏りのない家にできるのに。」と苦しい胸の内を話してくださいました。そんな中でお粥は大きな希望になっていると話してくれました。「以前は子どもが『何か食べたい…』と言っても何もあげられず、それがとてもつらかったけど、お粥を食べて帰ってきてくれるので、食べものをせがまれなくなって気持ちが楽になりました。」とおっしゃっていました。お父さんは私たちの訪問に合わせて、初めて幼稚園に出向かれたそうで、「娘が幼稚園でいきいきと勉強をしている姿を見て、嬉しくなった。」と話していました。お父さんご自身は、足が不自由だったこともあり、学校には小学2年生までしか通えなかったそうです。教育も充分に受けられず、自分で家族を養うことができないお父さんの心情はどのようなものでしょうか。お父さんはお子さんのことを優しいお顔で見ながら、「娘がしっかりと勉強をし、いつかは家族を支える存在になってくれたら嬉しいです。」と話されました。

アビシャイちゃん(5才)と家族
チェンド村では小学校にも行きました。給食のお粥は、保護者や村のボランティアのみなさんが朝の8時過ぎから作っていました。ちょうど子どもたちが登校してくる頃です。
チェンド村では、13才の小学5年生の男の子のお家に行きました。彼の家は山の中にあり、家ではお母さんと弟くんが待ってくれていました。彼は山を登って30分以上をかけて学校に向かいます。彼のお父さんは出稼ぎに行っていて、出稼ぎで稼いだお金で家庭を支えています。彼には将来、英語の先生になりたいという夢があります。インタビューにも少し英語で答えてくれ、一所懸命勉強をしているのだと感じました。彼に「あなたにとっての幸せは何ですか。」と聞くと、「幸せはありません。」と返答が返ってきました。「一番大変なことは何ですか。」と聞いてみると、「学校の制服と家で着る服が1枚ずつしかないことです。その洋服を見ると、とても悲しくなります。」と話していました。「学校で給食が始まる前は、お腹が空いて学校に行く力が出なかったけど、今は毎日学校に行って、友だちと話すのが好き。」と話してくれました。お母さんも「楽しいことや幸せなことはないけれど、子どもがお粥を食べられて嬉しいです。」と話しつつ、「かなうなら私も食べたい。」と本音を話してくれました。この家族のお話を聞いて、お粥が彼らの命をつないでいることを実感しました。

チェンド村で出会った男の子(写真中央)
どの村でも、村の皆さんは私たちを歓迎して、荷物を持ってくれたり、お昼ご飯を用意してくださったり、本当に私たちの支援に感謝されていることを感じました。
ただ、子どもたちは、4才の子は2才くらいに見えるほど背も低く、小さく、中にはおなかが極度に膨れる栄養不良に陥っている子どもが何人もいました。特に最近では気候変動により、雨季に雨が降らないことが多く、雨水に頼っているマラウイでは畑で十分な作物が育たず、食料不足が深刻になっています。そして、十分に食べることができない子どもたちは学校に行けず、悪循環へと陥ってしまいます。

プロジェクトで作られるお粥
現在はチティパ県で給食支援が行われていますが、支援開始当初の2014年に支援していた地区では、9年経った今でも住民たちの手で、自立して給食の提供が続けられており、このプロジェクトが、いかに支援に頼らず生きる力を育んでいるかということを知ることができました。
私は今回初めてマラウイ共和国に行きました。学校給食プロジェクトによって、多くの子どもたちが学校に行くことができるようになることを報告書を読んで知ってはいましたが、給食を当たり前のように食べてきた私は、そんなに給食がすごいものなのかと疑う気持ちを捨てきれずに現地へ向かいました。しかし、現実は私の想像を超えて、1日に何かを口にすることすらままならない家庭や、映像の中でしか見たことのない、小さく、おなかの膨らんだ栄養不良の子どもたちに出会い、とてもショックを受けました。

訪問したお宅の様子
給食と言っても、大豆やピーナッツは入ってはいるものの、お粥が一品という質素なものでした。それが彼らのいのちを繋ぎ、病気にならないための体力をつけているのだと、しみじみと実感しました。そして、そのお粥がすぐに彼らの貧困問題を解決することはできないけれど、確実に子ども達の命を繋ぎ、未来を拓くものであることがわかりました。
私には、洋服を買い替えたい、お家を建て替えたい、という全ての願いを叶える力はありませんが、一食の支援がご飯の食べられない子ども達の未来を拓くことを確信し、一食の実践を続けていきたいという思いが強くなりました。この運動を続けることで、さらに多くの困っている人たちのところに希望が届き、いつかは彼らが自身の手で洋服を買い、家を建て替え、夢を実現していくことを願って。
今後も一食事務局の一員として、一食実践をしてくださっているみなさまの祈りのこもったご浄財を、困難な状況でも懸命に生きている人びとに、確かな支援としてお届けしてまいります。